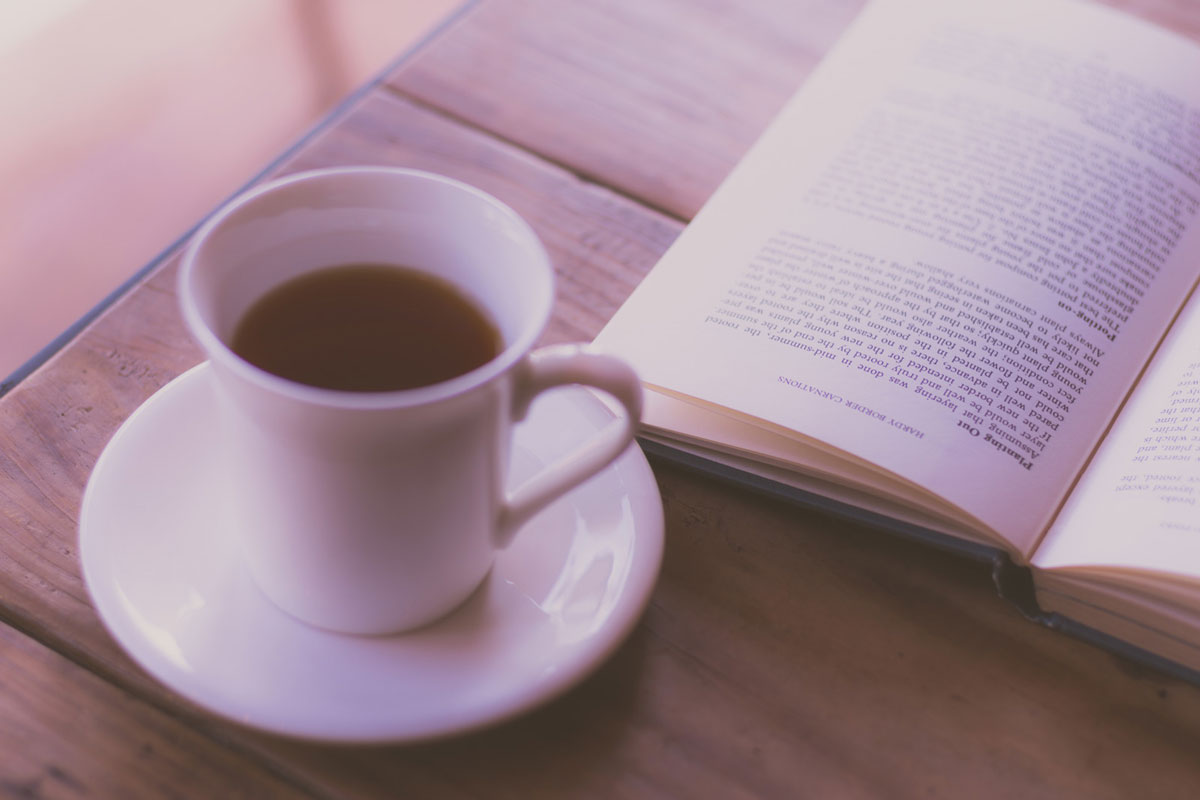
1977年(昭和52年)8月に、輸送と交通流理論の第7回国際会議が、京都国際会議場で開かれた。京都大学工学部土木工学科の米谷英二教授のこの分野への貢献を記念して、日本で初めて開催されたものである。
私は、交通流の研究を始めた当初、父の三高時代の級友である米谷英二教授の許しを得て、土木工学科の書庫に通い、Transportation Theoryや、Traffic Theoryに関する雑誌のバックナンバーを調査し、Wardropの交通流等時間配分論を見つけて、主たる研究テーマに選んだことを懐かしく思い出した。
西川禕一教授は、我々が仕上げてきた成果を英語の論文として、この学会に投稿された。[1]
幸い、我々の論文は40編中の一編として採択された。日本から採択された論文は6件であった。西川教授の英語での堂々たるご発表に感銘を受け、いつの日か英語で論文発表をする夢を果たしたいと思った。
この会議の国際アドバイザリーコミッティーメンバーは12人であり、John G Wardrop(University College London, U.K.)もその1人であった。大変嬉しかったのは、Wordrop氏がこの会議に出席され、親しくご挨拶ができたことであった。また、1974年米国出張で、IBMワトソンリサーチセンターにGazis博士をお訪ねしたとき、同席していた中国人のKai Ching Chuさんも、この会議で論文発表され、思いがけない再会が果たせた。
博士論文の集大成としての国際会議への参加を区切りとして、私は本来の仕事に復帰した。
恵那山トンネルのプロジェクトに長く関わった関係で、このプロジェクトのとりまとめを担当した神戸の制御製作所公共部と付合いが始まった。公共部は、公共インフラ施設のシステムとりまとめ部門として、受配電装置、ポンプ・ファン動力装置、それらの制御監視操作システムの開発設計製作を担当する部門である。
当時、制御装置は電磁リレー回路によるオンオフ制御装置が主に使用されていたが、工業用コンピュータや工学用コントローラの出現により、従来のリレー回路の役割が徐々に減少していた。制御製作所公共部では、下水処理の活性化汚泥処理プロセスの運用や、上水道の送排水システムの最適運転の仕事など、従来のリレーロジックでは解決できない課題への取組みが急がれていた。
恵那山トンネルの仕事を終え、博士論文をまとめている段階から、公共部の依頼研究が舞い込み始めた。私はグループの仲間と共にこれらの仕事に取組みはじめ、これらの新しい課題を抱えている製作所に強い興味を持つようになった。
[1]Y.Nhishikawa, I,Nakahori, “A network Theoretic formation and algorithms for traffic problem” P531-544, Proceedings of the 7th International Symposium on Transportation and Traffic Theory, Kyoto 1977

